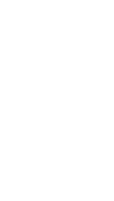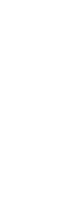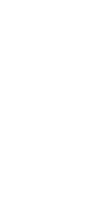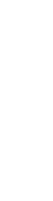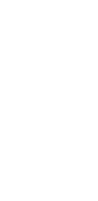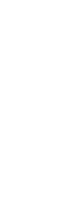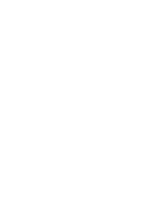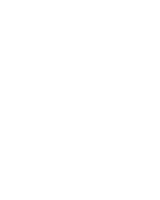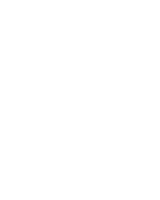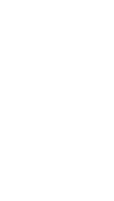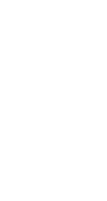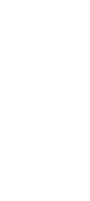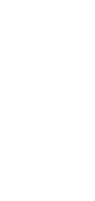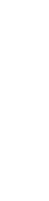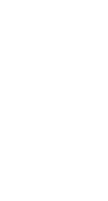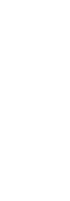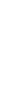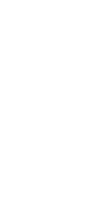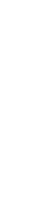091
本のデザイン
まちを育てる建築オランダ・ルームビークの
災害復興と住民参加
事故でまちが焼失したオランダ東部。復興コンペで当選した建築家の案は「一本の線もない」提案だった。住民参加の真価を問う一冊。
- 鄭弼溶 著
- W128 × H188 mm/156ページ
- 鹿島出版会
091
本のデザイン
まちを育てる建築オランダ・ルームビークの
災害復興と住民参加
カバー。住民参加を取り上げた本なので、本全体で求めたのは手作りの感触が伝わるような仕上がり。その一環として、住民参加の過程で使われた積み木のブロックやメモ用紙をマーク化して、本を通してのキーアイテムにしてみた
目次。目次ページは、本全体の雰囲気を端的に表すセクションになるように、そのデザイン作業に時間をかけることが多い。この目次ページは本の本編がはじまる大扉のページも兼ねているので、写真を多く取り入れた。人びとと建物の写真をミックスしてコラージュにすることで、「まち」の雰囲気を表そうとしている
プロローグ〈まちの焼失〉。マジックペンで粗く塗りたくったような手書き風の文字は、この本のためにつくったもの
第1章〈ヴィジョンを重ねる──復興計画とプロジェクトづくり〉、章扉ページ。手書き風の書体の数字を大きく
第1章。本文の基本フォーマットは明朝体の1段組。参加した住民に焦点を絞るために、人物写真の大半は人物の輪郭で切り抜き処理を行って背景から切り離している。その切り抜きの輪郭線はざくざくとハサミで切ったような荒い形で
第1章。地区全体の概要図。解説の該当箇所を示す矢印や範囲を表す波線などの図の一部の要素を手書き風にして、図面にありがちな冷たい印象を緩和
第2章〈「一本の線もない」提案──設計者の選定〉、章扉ページ。このあたりはブラック1色の印刷
第2章、〈ペーター・ヒューブナーによる提案〉。このセクションは提案書を紹介するために横罫ノートのような体裁にしている。本全体を通してときどき脈絡なく手書きの粗いイラストをアクセントとして挿入
第2章、コラムページ〈ゲルゼンキルヘンの総合学校〉。有機的な形状のトリミング処理
第3章〈先生へ渡されたメモ──こどもたちとの学校づくり〉、章扉ページ。巨大なメモをじっと見るこどもたち、みたいな絵柄
第3章、メモ1〈問題提起──本当にできるのか?〉。大小さまざまな写真サイズへ柔軟に対応できるように、本文は1段分の上下サイズがコンパクトな3段組みに。文字が小さくても読みやすいよう本文の書体はゴシック体に
第3章、メモ2〈自分の大きさを知る〉。プロジェクトの段階を示す数字とマークのメモ用紙の枚数を同じにすることで、段階が進むにつれて経験が蓄積される様子を示そうという試み
第3章の最終ページと、第4章〈「積み木」の集積──一緒につくるプロセス〉、章扉ページ
第4章、ステップ1〈思いをまずかたちにしてみる〉。ここはオレンジの特色1色とブラック1色の印刷。こげ茶色はオレンジとブラックを掛け合わせることで表している
第4章、ステップ5〈発表と議論、そしてまた作業へ〉。第3章のメモ用紙のマークと同じように、プロジェクトの段階を示す数字とマークの六角形の積み木の数を同じにすることで、経験が蓄積される様子を示している。模型の写真では、限られた紙面の中でも参加者の試行錯誤を重ねる様子ができるだけ伝わるように、模型の部品のグループごとに共通の印刷上の色を割りあてて、それぞれの模型の個性の違いが感じられるようにした
第4章の最終ページと、第5章〈ひとつとして同じもののない──建物の完成〉、章扉ページ
第5章。この全体図も手書き風に
第5章。ここはカラー(プロセス4色)印刷
第5章、竣工写真
第6章〈愛着と人のつながり──その後のルームビークとユーザーの声〉、章扉ページ
第6章、関係者へのインタビュー。関係者のことばはゴシック体の3段組み
第6章。このインタビューのセクションの人物写真は、切り抜き処理したものを薄い色で表した。そのため、テキストと重なりあってもお互いに干渉することがないので、できるだけ写真を大きくすることができる。また、その人物写真をインタビュー記事の小見出しと本文テキストに重ねることで、その3つがひとつの固まりであることを表すことができ、その結果、ページの余白と記事とのレイアウトのメリハリがついた。そしてそのメリハリのおかげで、本のノド部分で分断される記事もひとつの固まりであると示すことができたので、2ページに3つのインタビュー記事を掲載するというやや難しい課題を自然な形でなんとかクリアーできたと思う