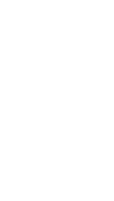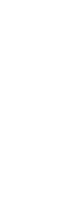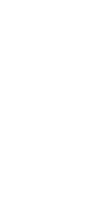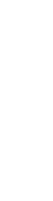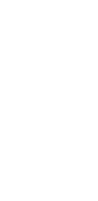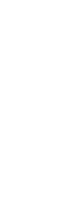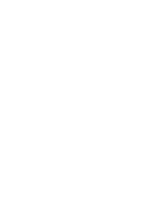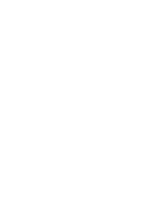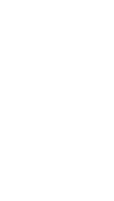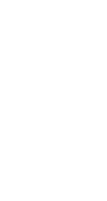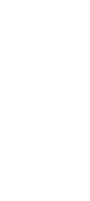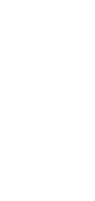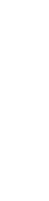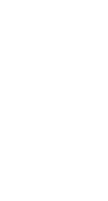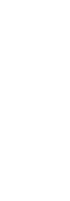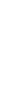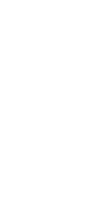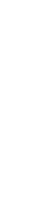格差社会と都市空間東京圏の社会地図
1990-2010
- 橋本健二、浅川達人 編著
- W148 × H210 mm/304ページ
- 鹿島出版会
格差社会と都市空間東京圏の社会地図
1990-2010
カバー。
本書では、多くのデータを用いて東京圏における格差の拡大を分析する。そのデータのひとつである「地域メッシュ統計図」をカバー全体に大きく広げて掲載
口絵ページ。
本の冒頭に代表的な統計図をカラー(プロセス4色)で掲載。
図の中においてデータ数値の大小を色で表す色面の配色を、印刷時の掲載サイズや使用インキの色数をもとに検討した。用意した色は、データの数値が低いものから高いものへと変化するにつれて、うすいグレー→うすい青→青→濃い青、へと次第に変化していく最大10種類。色の濃度に加えて青味も変化させることで、図全体を見た時にデータの特徴や傾向が一目でわかるようにしている
本文、目次ページ。
目次には多くの種類の文字要素がそこに含まれるので、それらを見やすく整理しながら、なおかつ、できれば本全体の雰囲気をあらわす「顔」の役割も果たせるように、文字サイズと行間隔のバランスを調整している
本文、部の扉ページ。
扉のページは、その直前まで続いてきたページとは視覚的に大きく異なる特徴を持つことによって、それまでの本の内容の流れをドアのようにいったん遮断し、リセットして、新しい流れの起点となることができる。
本書では1ページの全面を統計図で敷き詰めて、部の扉ページとした。すべての各扉の図の元はカバーに使用したただひとつの統計図だが、図のなかのそれぞれ異なる一部分でトリミングし、拡大して使用することで、同じ図に見えることを避けながら絵柄のバリエーションを増やしている。視覚的素材があまり豊富にない中での工夫のひとつ
本文、標準的なページ。
色はモノクロで、本文組は縦の2段組。
脚注がある場合、本書では章や本の末尾にまとめることはせず、見開きごとに左ページの末尾部分に1段分の高さで添える
本文、統計図入りのページ1。
カラーページ用と同じようにモノクロページ用の統計図も、図の中の色面の配色を検討。モノクロの場合はカラーの場合より使える色の範囲が限られるため、より慎重に検討し、それぞれの色面に対して以下のように色を割りあてた。
- 最高値のグループ:グレー100%(=黒)である地形線と隣り合ったときにその差がわかる濃度として、グレー90%
- 最低値のグループ:グレー0%(=白地)との差がわかる濃度として、グレー15%
- 中間の値のグループ:上の2つの濃度の中間を、4つの段階にわけたグレー
合計で、6種類のグレーを使用している
本文、統計図入りのページ2。
統計図を配置する際は、図の中に多くの情報がつまっているため、掲載サイズをできるだけ大きくしたかった。ある図ともう一方の図の、主要部分同士がぎりぎり重ならない範囲で図同士を重ねたり、小見出しや凡例、キャプションの位置を、図によって変えたりしている
本文、統計図入りのページ3。
統計図をグループごとに配置する場合、どの図がそのグループに属するのかを明確に示すために、図の並べ方や間隔、要素の配置などをそれぞれのケースで細かく変えている。特にキャプションは1グループにつき常に1つ付属するためにその役割は大きいので、位置と形に配慮した。
たとえばこれらのページでは、図がそれぞれ6、5、4つあるが、すべて3つのグループに分かれている。
図が6、5つのケースでは、キャプションをグループの下に1行で流した。キャプションの横幅サイズを長くすることで、グループ全体を支える「皿」としての役割と、ほかのグループとの間を区切る「境界線」の役割の2役をその形で示し、グループの範囲を明確にしようというもの。
図が4つのケースでは、空いている余白スペースの中で自由に動かしやすいよう、キャプションの文の中で何回か改行して横幅サイズをコンパクトにした。それをできるだけグループに近い位置に添えることでグループを示している
本文、統計図入りのページ4。
このページでは、グループの数は4つ。違うグループに属する2つの図が横隣りに揃って並ぶと、同じグループに属しているように見えてしまうおそれがあるので、それを避けるためにあえて位置を上下にすこしずらした
本文、統計図入りのページ5。
この見開きはまるごと2ページ分を使って、縦列に同じ階級の図を、横行に同じ年次の図を、それぞれ並べた表になっている
本文、グラフ入りのページ1。
統計図と同様に、グラフの中でデータの数値の大小を表す色面の配色を、それぞれ以下のように色を割りあてた。
- 最高値のグループ:グレー100%(=黒)である軸線や補助線と隣り合ったときにその差がわかる濃度として、グレー90%
- 最低値のグループ:細い線でも白地との差がはっきりわかる濃度として、グレー20%
- 中間のグループ:上の2つの濃度の中間を、3つの段階にわけたグレー
合計で、5種類のグレーを使用している
本文、グラフ入りのページ2。
帯グラフや折れ線グラフは、紙面のスペースに余裕のあまりない中で多くのグラフを掲載するために、データの主旨を読み取れる範囲内で、グラフ全体を縦方向にできるだけ圧縮するようコンパクトに変形することが多い
本文、グラフ入りのページ3。
折れ線グラフは、グラフの中で多くの折れ線が込み入っているので、どの折れ線でも線を辿ることができるように、色の濃度と実線・破線の線タイプを折れ線ごとに使い分け、そのラベルを折れ線のすぐ近くに配置して、引き出し線でつないだ
本文、表入りのページ。
本書では表も多く掲載。複雑な内容を読み解いて、それらがわかりやすく見えるように組み立てている。
たとえば左側の表では、表の小さいグループが集まって、すこし大きいグループになり、さらにそれらが集まってより大きいグループになった、という各構成グループの関係を意識して整頓している
本文、地図のページ。
本の末尾には東京都と南関東の市区町村図を収録