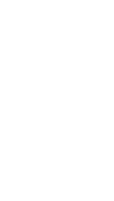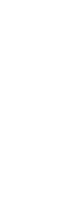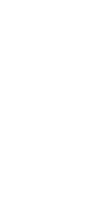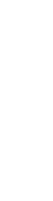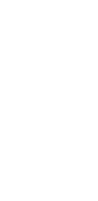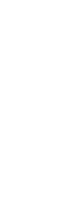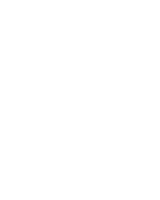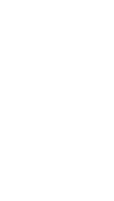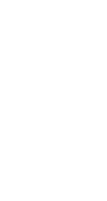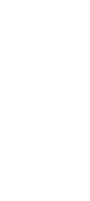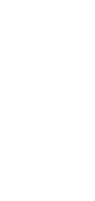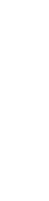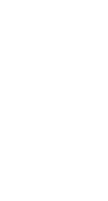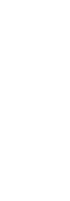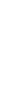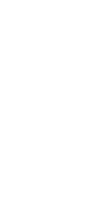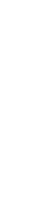116
本のデザイン
農福連携の
「里マチ」づくり
「農」のある地域を再生し、自然と人間が共生する新たな「里マチ」の創生を目指す。そのための豊富な事例・解説を紹介するガイドブック。
- 濱田健司 著
- W148 × H210 mm/160ページ
- 鹿島出版会
116
本のデザイン
農福連携の
「里マチ」づくり
カバー。自然と人間が共生する新たな「里マチ」。野菜や動物、畑や機械など、農にまつわるものを俯瞰の視点で描いて、それらをランダムなスケール感と整然とした並べ方でぎゅっと凝縮した、シンボルマークのようなコラージュ
見返し2。本の冒頭に掲げる理想のイメージとして、絵本『庭をつくろう!』3の絵を見返しに掲載。緑の特色1色で印刷
- 見返し
- 本の表紙と本文を接合して補強するために、表紙の内側に貼られる用紙のこと。二つ折りにした用紙の半分を表紙の内側に貼り付け、もう一方を最初のフリーページとして使用する。一般的には無地の色紙をなにも印刷しないで用いることが多い
2
- 『庭をつくろう!』
- 著者:ゲルダ・ミューラー/訳者:ふしみみさを/出版:あすなろ書房
3
本文、イントロダクション。〈里マチ〉のひとつの例をイラストとともに描写して、その具体的なイメージを読者に共有してもらう
イントロダクション。本文の冒頭にあたるこれらのセクションは、見返しと同様に緑の特色1色で印刷
〈農福連携宣言〉。目指す社会のあり方を宣言する。カバーで用いたコラージュのマークを右ページに紋章のような雰囲気で配置し、それに対向するように左ページに文をおいて、宣言書のような見開きページにしてみた
目次。ここも引き続き緑の特色を使用
〈はじめに──地域創生・再生を導く新たな連携のカタチ〉。緑の特色を用いるのはこの右ページまで。左ページからはブラック1色。本文のフォーマットは縦の1段組み
第1章〈これまでの福祉・農業・地域〉。福祉と農業の現状を統計データとともに解説
第3章〈農生業とは何か〉。事例としてスウェーデンでの取り組みを紹介
第3章〈農生業とは何か〉
第4章〈地域に生きる農福連携──いろいろな取り組み〉。季刊誌『コトノネ』2より。このセクションの本文は2段組み
- 『コトノネ』
- 障害者の就労をテーマにした季刊誌。出版:はたらくよろこびデザイン室
2
第4章。季刊誌『コトノネ』より
第4章。季刊誌『コトノネ』より
第5章〈農福連携に取り組むために〉。〈農から福へ──作業委託までの流れ〉を表したフローチャート
第5章。調査表やマッチング表、作業カルテ、契約書などのサンプル
第5章、〈福から農へ──農業へ取り組むまでの流れ〉。先の〈農から福へ〉とは逆の方向の場合のフローチャート
第5章、〈農福連携の実施に役立つ情報〉。取り組みをサポートする助成金制度や関係機関の問い合わせ先などをリスト形式で紹介。本編とは別の付属的な情報ページとして背景をグレーにしている。また、リストはその項目の内容をそのままテキストで流していくだけでは無味乾燥になりがちなので、それを避けるためにここではひとつの項目にひとつの矩形をわりあてて、ブロック状に並べている。この手法は、それぞれの項目をほかの項目から切り離して引き立たせることができるという長所をもつが、それだけに、ある項目とある項目の間で内容の量の違いが大きいと、その差も際立って見せてしまうという難点もあわせもつので、ときに注意が必要
第5章、〈農福連携の実施に役立つ情報〉。この本は本文が縦組みなので、ページの内容は本来右から左へ流れていく。一方このセクションのリスト項目は、ウェブサイトアドレスなどの英文を記載しやすくするために横組を採用しているので、ページとは逆にその内容は左から右へと流れていく。「では、リストのカテゴリーの小見出しを設ける場合はどうする?」と考えた時にしばらく困ってしまったが、上の2つの中間にあたるものとみなして、右から左へのページの流れに対して左から右へ流れるテキストを右揃えにしたものを衝立のように立ててカテゴリーを仕切る、という形にしてみた