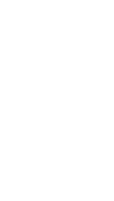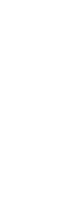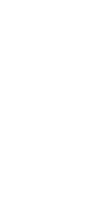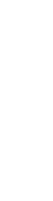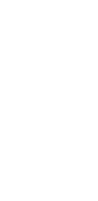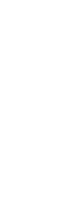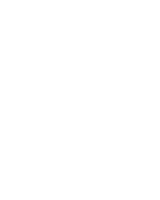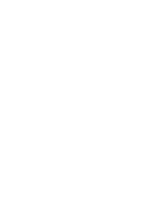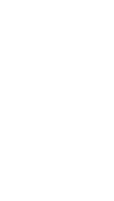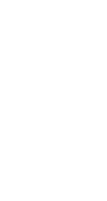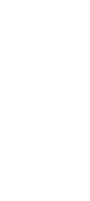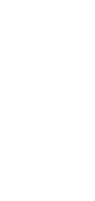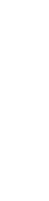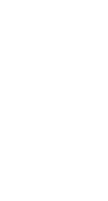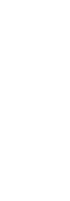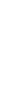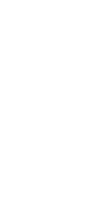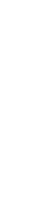早稲田建築学報
- 早稲田大学大学院建築学専攻
早稲田大学建築学科
早稲田大学建築学研究所 - W220 × H280 mm/80ページ
- 建築資料研究社
早稲田建築学報
表紙。
当初の段階では、各号ごとの表紙に写真や図などの図版を掲載する方針ではあったが、実際にそれらの素材をどの程度入手できるのかが見通せなかったので、書名のロゴは以下の方針で作成した。
- 万が一よい素材を入手できない場合でも、表紙としての品質と「張り」を保てるように、あらかじめ大きめのサイズにして存在感をもたせる
- 逆に、もしよい素材が入手できた場合には、そちらを引き立たせるためにある程度コンパクトなサイズに収まって存在感を減らす、というようなことのできる柔軟性もほしい
- 以上を両立させるためにロゴは、その配置場所、文字要素の組み立て方、全体の形状、飾り罫線の数やサイズ、などをひとつの種類に固定しないで、各号で変更できるものとする
目次。
目次には多くの種類の文字要素がそこに含まれるので、それらを見やすく整理しながら、加えてできれば本全体の雰囲気をあらわす「顔」の役割も果たせるように、文字のサイズと間隔のバランスを注意深く調整
特集〈「野」生の建築史〉。早稲田大学の建築史学の系譜を概観し、建築と歴史の関係性を論じる。
特集の英字タイトルは、「architecture」と「history」の2つの単語の中にある同じ文字同士をつなげたり、位置をそろえたりして、建築と歴史との密接な関係を表現してみた
特集。
この特集と表紙は、キーカラーである赤色の特色1色とブラック1色の計2色印刷。
見開き上部のメインの記事で本題を論じ、下部のサブの記事では補足的なトピックを紹介する。複数のページにわたって、2つのタイプの記事を並行して水平方向へ流していくレイアウト構成
特集。学生アンケート〈未来に残したい建築〉。
レイアウトは以下のようなグループで構成している。
- アンケート結果の上位にあがった建築の写真。アンケートの得票数に応じて写真のサイズに大小のメリハリをつけて、見開きの中でもっとも目立つグループにする
- アンケート結果のその他すべての建築名のリスト。大量のリスト項目をコンパクトにぎゅっと凝縮してまとめる
- 編集部の推す建築の紹介。整然と並べる
- 学生のコメントの抜粋。上の3つのグループの間にできた隙間スペースに、アクセントとしてランダムに散りばめて、紙面に不規則性と活力を添える
〈卒業計画優秀作品〉。学生の優秀作品を紹介する。
本全体に一貫するフォーマットとして、見開きの最も下の帯状の部分には、見出しなどをおさめる容れ物とするためと、内容を引き立たせる余白とするための、2つの目的のためにスペースを空けている。セクションの冒頭のページの場合にはこのスペースにその大見出しを配置する。
一般的にこのスペースにおくことの多いノンブル1は、本書の場合はこのスペースを避けて、そのやや上方の小口側においている(次へつづく)
- ノンブル
- 本や冊子のページの端に記載されている、そのページの番号を指す数字
(前からのつづき)〈修士計画優秀作品〉。
見開きの最も下の帯状の部分には、このページのようにそのページがセクションの冒頭ページでなければ、柱1を配置する。
〈優秀作品〉のページは、ひとつの作品につき以下の3つの要素グループでレイアウトを構成。
- 作品概要文:グループ内の文字情報をできるだけコンパクトにまとめる
- 作品タイトル:作品概要文と同様
- 作品写真:上の2グループをまとめたあとに残った広いスペースを使って作品写真を引き立たせる
- 柱
- はしら。書籍のページの端のあたりに入れられる見出しの一種。一般的には書名、章題、節見出しなどを小さいサイズで記すことで、現在のページが何について書いているのかを読者に知らせたり、読者が読みたいページを素早く見つける補助をしたりする、索引の役割を担う
〈卒業計画公開講評会〉。講評会で交わされた教授陣の講評と学生の応答を収録。
卒業計画を総括するページとして、個々の作品紹介のページよりすこし格上に見える体裁にしたかったため、このページは背景を黒色に、文字を白抜きに
この号の特集は〈『建築 × 展覧会』の可能性〉。
特集の英字タイトルを前号と同じように表紙に大きく掲載。「architecture」と「exhibition」の2つの文字を袋文字1にし、その輪郭線どうしを放射状の線でつなげて、プロジェクションあるいはネオンライト管を想起させる形態にすることで、「建築」と「展示」の関係を表現してみた
- 袋文字
- ふくろもじ。文字の装飾法のひとつ。文字の内部には色付けを行わず、文字を縁取るようにその輪郭部分にのみ色付けを行う
特集〈『建築 × 展覧会』の可能性〉。
この特集と表紙は、キーカラーである水色の特色1色とブラック1色の計2色印刷。
特集の英字タイトルは、紙面に視覚的なインパクトを与えるために見開きの中央に堂々とおくことを想定してつくってみたが、実際においてみると、「exhibition」の「b」がちょうど見開きのノド部分に位置するためにかなり見にくくなってしまう、という問題があることがわかった。こういう場合に通常は、以下の2つのどちらかを行うことが多い。
- タイトルを中央におくことはもうあきらめて、ノド部分が文字と文字の間(たとえば「b」と「i」の間)をちょうど通るように、タイトル全体をすこし小さくして左か右に位置をすこしずらす
- あくまでタイトルを中央におくために、実際に本を開いた際に「b」が自然に見えるように、左ページ用と右ページ用の2つの「b」を作成して、それぞれで位置や文字の形を調整する
後者は作業が大変そうなため、前者で十分な結果が得られることを当初期待したのだが、検討した結果、前者だと紙面のインパクトが後者にくらべてどうしても劣ってしまうと感じたので、最終的に後者を採用している
特集。学生アンケート〈早稲田建築学生はこんな「建築展」を見ている〉。
このアンケートのページでは特に学生主導の展示を2つ取り上げて紹介している。その展示のアンケート集計の結果とその展示の内容の概要を、引出線でつないで絡めながら説明する構成。
前号のアンケートのページと同様に、集まったコメントの一部を付箋に記してべたべたランダムに貼りつけるように配置した。その不規則性によって、数字の集まりの集計データから受ける冷たい印象を緩和しようとしている
特集。座談会〈変容する「建築展」〉。
このセクションも引出線を用いている。特集の英字タイトルの袋文字の線とあわせて、見開きを斜めに横断するこれらのライン群を、特集全体の視覚的な特徴のひとつとしている
〈卒業計画優秀作品〉。
ここはカラーページ。1見開きに1組を掲載するケース。
作品の制作者のポートレイト写真は個性が様々なので、ほかのポートレイト写真との全体的な統一感を確保するために、以下のようなルールをたてた。
- 人物の輪郭で切り抜き処理を行って背景を削除する
- その色を作品写真へ干渉させないために、写真全体をブラック1色に変換する
(次へつづく)
(前からのつづき)
〈卒業計画優秀作品〉。
ここはモノクロページ。1見開きに4組を掲載するケース。
学生のポートレート写真をブラック1色にしたもうひとつの理由としては、もし、カラーページにあるポートレートがそのままカラーで掲載されていて、読み手がめくった次のページがモノクロページだったら、読み手に地味な印象を与えるかもしれない、という懸念がすこしあったことが挙げられる。それを避けるため、カラーページにあらかじめモノクロの要素を含めておくことによって、カラーページとモノクロページの間で生じる鮮やかさの印象のギャップをできるだけ埋めてならそうとしている
〈修士計画公開講評会〉。
どの作品についての講評なのかを読み手に明快に示すために、その近くに小さめの作品写真と掲載ページのページ番号を挿入している
この号の特集は「木」に着目。「木と火と建築」という視点から見る、戦後日本における建築の現代史
特集〈木と火と建築の現代史〉。
木造建築の統計グラフを、図版のひとつとしてではなくページの背景として配置した。それには以下の目的がある。
- 時間を横軸とした単なるデータの集積という役割ではなく、歴史の一側面を記録した履歴という役割を統計グラフに与えることで、時間と歴史の流れを背景にしているという深遠な雰囲気を本文に添えること
- 本文にできるだけ近い場所にグラフを配置して、ふたつを視覚的に絡ませることで、読み手の本文の読解を補助する効果を上げること
- グラフを背景化して、グラフとそのほかの要素とを、別のレイヤーとして視覚的に明確にわけることで、紙面に奥行き感と立体感を加えること
特集の英字タイトルの文字には縞模様をあしらった。それぞれの文字によって以下のように模様を変えている
- 「建築」の文字:構造の柱の様子を表すものとして、垂直線の縞模様を使用
- 「木」の文字:木の幹の年輪の模様を表すものとして、円弧状の縞模様を使用
- 「火」の文字:炎のゆらめきの動きを表すものとして、波状の縞模様を使用
特集。
この号のキーカラーはオレンジイエロー。カラー(プロセス4色)で印刷
特集
〈修士計画優秀作品〉。
1見開きに4組を掲載するケース。この見開きはカラーで印刷。
この号はカラーページが大幅に増えたり、前号まで別のページに一括してまとめていた教授陣による講評が、各作品の概要文の中に掲載されたりなど、いくつかの変更があった。体裁の細かい部分にも変更したところがあったものの、基本フォーマットは前号までのものをほぼそのまま踏襲している
〈卒業計画優秀作品〉。
1見開きに1組を掲載するケース
〈早稲田建築、6年間一貫カリキュラム〉。学部から大学院までの6年間の教育過程を解説する。
レイアウトは、以下のように構成している。
- 全ての課程を表す階段状の線。これを見開きを貫く軸とする
- その上には各学年で学ぶ全教科のリスト
- その下には代表的な教科を抜粋してその詳しい紹介