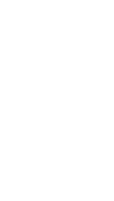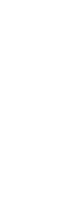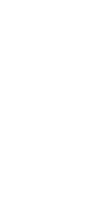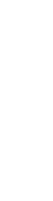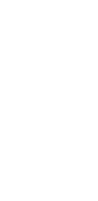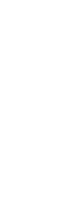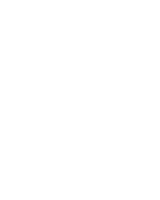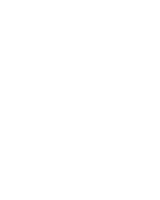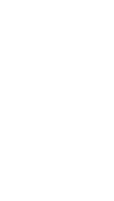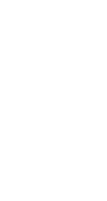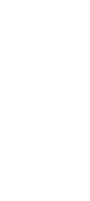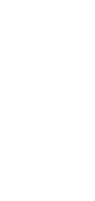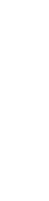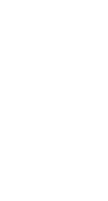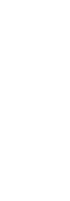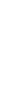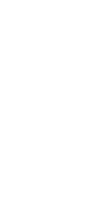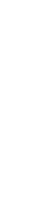168
本のデザイン
「地区の家」と
「屋根のある広場」イタリア発・
公共建築のつくりかた
日本と同様に格差などの社会問題を抱えるイタリア。6つの魅力的な「みんなの場所」を通してこれからの公共建築のありかたを論じる。
- 小篠隆生、小松尚 共著
- W148 × H210 mm/220ページ
- 鹿島出版会
168
本のデザイン
「地区の家」と
「屋根のある広場」イタリア発・
公共建築のつくりかた
カバー。「地区の家」と「屋根のある広場」。それら2つを表す写真をそれぞれ素朴なシンボルマークのシルエットでトリミングして、ブロック状に上下に積んで、市民を包み込む様子を表現
目次(口絵)。「地区の家」とは自分の地区のために市民がなにかを行える場所。そのシンボルマークをアイキャッチとして扉に大きく配置。マークの下にはエピグラフ2的なテキストを記した
- エピグラフ
- 本や章などのはじめにおく句、引用、詩などの短文のこと。内容を暗示したり、要点を示唆したりするためにおかれる
2
目次(口絵)。本文のなかからピックアップした代表的な写真をカラーでここで先に紹介しながら、章のタイトルとそのノンブル2を記すことで、目次ページと口絵ページのふたつの役割をこのページに担わせている
- ノンブル
- 本や冊子のページの端に記載されている、そのページの番号を指す数字
2
目次(口絵)。「屋根のある広場」とは市民が集って「知」とつながることのできる図書館。その扉も同様に
〈詳細目次〉。目次(口絵)のすぐあとに、念のために標準的な文字のみの目次ページも備えた。右ページは小扉ページ
〈はじめに〉。本文は基本的に横1段組。
第1部〈市民がつくる、みんなの場所「地区の家」〉。部の扉ページでは、くつろぐ市民の写真をその内部に収めるシンボルマークを大きく配置した
第1部、第1章〈地域の「透明な場所」をつくる〉。トリノ市の事例として〈カッシーナ・ロッカフランカ〉を紹介
第1部、第1章〈地域の「透明な場所」をつくる〉。本書では写真を半ページほどのサイズで掲載するケースが多い。その場合は写真をページの幅ぎりぎりのサイズまで大きく掲載して、三方を裁ち落とさずに白フチで囲んでいる
第1部、第1章〈地域の「透明な場所」をつくる〉、図〈ロッカフランカの設立プロセス〉。本書では設立過程や財務状況などの情報も図や表で多く掲載
第1部、第2章〈マルチエスニックの拠点として〉、図〈サンサルヴァリオの設立プロセス〉。〈設立プロセス〉など、各章で共通して示される図では、それぞれの図を比較しやすいように、同じタイプの要素には共通して同じ体裁を割りあてた。たとえば、設立プロセスにおけるもっとも重要なトピックには四角と文字にそれぞれ黒色と白色を用いたり、設立プロセスを3つの段階に分けて説明する部分には段階ごとに固有の色を割りあてたりしている
第1部、第2章、図〈サンサルヴァリオの改修後平面図〉。本書で掲載される図表は、写真、設計図、模式図、日程表、財務表などとその種類が多様であり、その中の文字要素も多いため、それらの図の近くにおかれたときに埋もれることのないように、図表のキャプションには太い書体を用いて存在感を強めている
第1部、第2章。写真のサイズのタイプは、(先に説明した)幅が1ページ分の大サイズと、2分の1ページ分の小サイズの、シンプルに2種類のみ。それらを見開きページの上部に掲げ、テキストは下部に流す、というのが基本的なレイアウトフォーマット
第1部、第3章〈経験を活かし新たな展開へ〉、図〈ヴィア・バルデアの設立プロセス〉。写真と図はどちらもできるだけ大きいサイズに拡大したいが、図の幅のサイズを、写真の場合と同じようにページの端まで拡大すると、写真の場合には感じられなかったパンパンに張ちきれそうな膨満感を感じたので、写真の場合より幅サイズをやや小さくしてまわりに余白をすこし設けてみたところ、膨満感が消えてページに落ち着きをもたらすことができた(次へつづく)
第1部、第3章。(前からのつづき)じつは、「違う種類の要素に対して幅のサイズを揃えようとする」ことは、当初に写真と本文との間でも試している。そのサイズをいろいろ変えて検討してみたが、写真の幅サイズが小さすぎたり、逆に本文の幅サイズが大きすぎたりして、うまくいかなかった(次へつづく)
第1部、第3章。(前からのつづき)最終的には写真の幅と本文の幅を同じサイズに揃える考えはやめにして、それぞれ独立したサイズを用いることにした。ただ、そんなシンプルな決定に至るまでにけっこうな時間をかけて悩んでしまった。はじめに「すべての要素の幅サイズを揃える」という考えに囚われてしまったのがそもそもの発端で、その必要性は一切なかったのだが、ときにそういう落とし穴にはまってしばらく出てこられなくなってしまうのである
第1部、まとめ〈「地区の家」から学ぶ〉。部の末尾では、イタリアの事例から学べることをまとめる。本文を横2段組にして、1段組の本編から流れが変わったことを読み手に示している
第2部〈知と市民をつなぐ「屋根のある広場」〉。警官(あるいは警備員)が図書館で読書中。なおすべての写真に対して、階調やコントラストが印刷時に最適になるように色の調整を行っている
第2部、第1章〈市民の場所、そして文化の拠点をつくる〉。この見開きは、本書では数少ない縦位置の写真を用いるケース
第2部、第1章。左ページは大サイズの写真1点、右ページは小サイズの写真4点。このようなケースのレイアウト作業は一見するとごく簡単に思われるかもしれないが、実際には当初の見込みとは異なってそれほど簡単ではなかった。各ケースでそれぞれほかのページとすこしだけ異なってしまうために、すべて同じに見えるように追加の微調整を必要とするケースが多く生じた。仕上がりと作業効率のバランスが良い基本フォーマットをどうつくるのかが、課題として残る
第2部、まとめ〈「屋根のある広場」から学ぶ〉