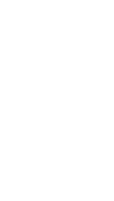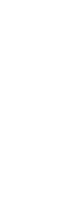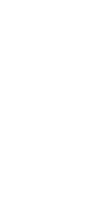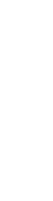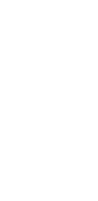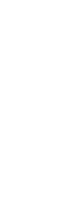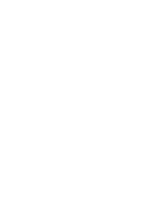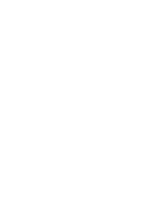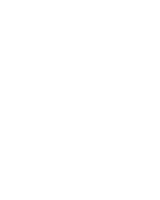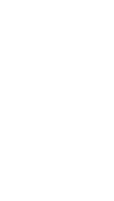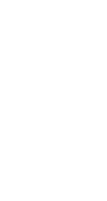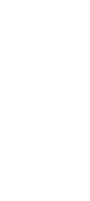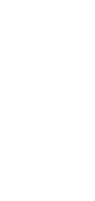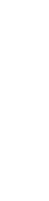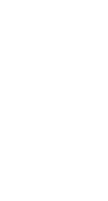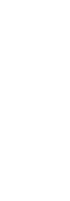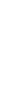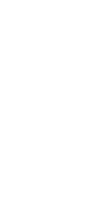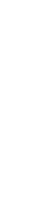復興を実装する東日本大震災からの
建築・地域再生
- 小野田泰明、佃悠、鈴木さち 共著
- W148 × H210 mm/350ページ
- 鹿島出版会
復興を実装する東日本大震災からの
建築・地域再生
カバー。
復興に必要な時間と、その重み。それをカバーでさりげなく示唆するために、発災からの暦年を示す数字とその1年間を区切る水平方向の罫線を、日程表のような体裁で縦方向に並べている。
背景には、ある被災地の復興検討図をもとに加工した画像を敷いた
本文、章の扉ページ。
8つからなる各章の扉ページには、カバーに用いた地図を薄い色調に色変換して、ページごとにそれぞれトリミングの位置を変えて背景に敷いている
本文、標準的なページ。
基本的な本文組みは、縦の2段組。
図版を入れ込む場合は、本文の上段か下段に1段分のスペースを空けて、あるいは上段と下段の両方を使って2段分のスペースを空けて、そこに配置する
本文ページ。
本書ではグラフ、表、図面など多くの図版を掲載しており、特にその種類が豊富なのが特徴。それらはもともと著者側が作成したもので、そのデータを土台として、文字や線の体裁を統一したり、使用スペースにあわせて図のなかの要素の位置関係を変更したりするために、こちらでほぼ新たに作り直している。
以下では、それらのページを図版のタイプ別に紹介していきたい
(これは東日本大震災の被災地域を示した図)
図版タイプ:帯グラフ(横)。
帯グラフは、全体に対しての各項目の割合を表すのに用いられる。割合の合計が必ず100%であることから、グラフを描き起こす際に、帯の長さや目盛線の刻みを1種類に統一できる。雛形をひとつつくればそれを元に大量に複製利用できるので、レイアウト作業の効率面でたいへんありがたいタイプなのである。
本書では帯1本分の縦幅サイズは、本全体を通して基本的に1種類に統一している。
(次へつづく)
(前からのつづき)
帯グラフの「帯」の部分は、各項目に対応する色面の小片で分割される。本書では、それらの色面の色を基本的に最大で5種類と設定。5種類の場合の最も濃い色と薄い色をそれぞれ「5」と「1」とすると、「5→1→3→4→2」の順に並べている。薄い色のペアである1と2、2と3は見た目の濃度が近いので、それらを隣り合わせにしないことで色面の間の境界部分をくっきりさせようとするねらい。
凡例0は帯群の右側に縦組の形でコンパクトに配置して、できるだけ多くのグラフをページの縦方向に積めるようにしている
- 凡例
- はんれい。グラフ内で使われている線や棒、色面などの色や形が、それぞれ何を示しているのかを説明するラベル
図版タイプ:帯グラフ(縦)と棒グラフ(縦)。
本書でいくつかみられるこのタイプは、2種類のグラフが上下にペアを組むことで複合グラフを形成している。
まず帯グラフ(縦)は、その特徴は帯グラフ(横)とほぼ同じ。体裁の面で、凡例をデータ図の右側に配置する点などを帯グラフ(横)と同じにしている。
このグラフでは、帯のなかの色面の色を、基本の最大5種類から7種類に増加している。グレーのベタ面の濃淡だけで色面を表す場合、種別の数がおおよそ「5」か「6」を超えると、それぞれの色面同士の色が似てきてしまうために区別しにくくなってくる。そこでここでは、縞模様を上からそれらに透かしたものを新たなタイプの色面として加えることで(ここでは3つを追加)、5種類を超える数の種別を可能にしている。
(次へつづく)
(前からのつづき)
もう一方のグラフである棒グラフは、棒の長さが割合ではなく絶対量を表す。そのため帯グラフとは異なって、棒の長さの最大サイズと目盛線の刻みを、各グラフごとに設定しなくてはならないのは仕方ないところである。
この棒グラフでは、そのデータの数値を帯グラフと同様に棒の内部か近い位置に示したかったが、帯グラフとは異なって1項目につきデータ値の個数が3つと多かったのであきらめた。その代わり、データ値の文字を縦に3つ積んで値のグループをつくり、それらを上下に交互にずらして配置した。そうすることで、ある棒グループに対してどの値グループが対応しているのかを、限られたスペースの中でも明確に示そうとしている
図版タイプ:地図(統計地図)と各種グラフ。
海外の事例として紹介する地域ごとに、統計データを地図と各種グラフで説明している。各地域ごとにデータの項目の種類がすこしずつ異なるが、同じ種類のデータ項目に対しては色やサイズなどに同じ体裁を与えることによって、複数の地域を比較しやすくなるようにできるだけ配慮した
(次へつづく)
(前からのつづき)
これらのページのレイアウト作業時に、折れ線グラフの「折れ線」について気づくことがひとつあった。折れ線と横軸線との間の面を固有の色で塗りこめた「色面あり」のグラフは、「色面なし」で描画した場合にくらべて、データの特徴を明快に示すことができるのである。著者側で作成した原稿にこのグラフがあるのをみて、はじめてその利点に気づくことができた(はい、今さらなのですが……)。
特にグラフの掲載サイズが小さい場合にその効果は大きいと思う。また、「色面あり/色面なし」両方の場合を併用することで、「あり/なし」どちらか一方のみの場合とくらべて、表現できる範囲が広がることがわかったのも収穫であった
図版タイプ:地図(土地利用図)。
復興事例として紹介する被災地ごとに、過去4つの年代と現在における土地利用図を掲載。
現在の地図のなかの焦点をあてたい箇所(防災集団移転、災害公営住宅など)は、地図全体にくらべるとごく小さい部分でしかないので、周囲の中に埋没してしまうおそれがあった。そこで、それらの部分のグレーの濃度を50%以上にまで濃くし、同時にそれ以外の地図全体の濃度を約25%前後にまで均一にうすくして、1枚の地図を濃淡2枚のレイヤーに分けてそれらを重ねたかのように見せることで、前者の見やすさを確保した。
なお、このような線図のなかの線は、印刷時にクリアーに仕上がるように、すべてその線幅を0.1mm以上の太さに統一している
図版タイプ:建築図面。
復興事例として紹介する被災地で建設された、災害公営住宅の図面を掲載。さきに説明した土地利用図と同様、線図の中の線は、すべてその線幅を0.1mm以上の太さに統一している
図版タイプ:エリア図と密度図。
エリア図は、「住民が顔をあわせる場所」や「食事をする場所」といった、ある条件を満たす特定の範囲を示す図。ここでは、敷地図や間取り図の上に円形の色面を透かして上から載せることによって、その範囲を示している。
密度図は、ある密度の値がどの部分で低くてどの部分で高いのかという、平面上の密度の分布の状態を示す図。ここでは、間取り図を格子状に分割し、その内部をその部分における密度に比例した濃度で塗りつぶすことで、住宅内における家具の密度を示している。
この掲載サイズだとひとつの格子のサイズがかなり小さいので、格子の境界線(この場合、格子と格子を隔てる白色の細い線)を描くかどうかについて、以下の2つの間でかなり迷ってしまった。
- 境界線を描く場合:格子間の境界は明確になるが、もともと小さい格子の色面の面積が、境界線に圧迫されてさらに小さくなってしまう
- 境界線を描かない場合:格子の色面の面積は境界線に圧迫されず本来のサイズを保てるが、格子間の境界が曖昧になってしまう
迷った末に、後者の場合は同じ濃度の格子同士が視覚的に一体化してしまって、個々の格子が格子として見えないおそれがあると思い、前者を採用することにした
図版タイプ:表。
本書では、表が複雑な場合でも読み解きやすくなるように、行の罫線のタイプを以下のようにランク分けして、それぞれの行の種類や位置に応じて適用している。
- ランクA:実線、太め、濃いめ(1番目が線の外形、2番目が線の太さ、3番目が線の色の濃度。以下においても同様)。表全体を上下から挟む形でその輪郭を示し、本文ブロックとの境界を明確にする。もっとも強い区切り線
- ランクB:実線、太め、うすめ。表ヘッダと表ボディとの間を区切る
- ランクC:実線、細め、うすめ。いくつかの行をまとめてグループ化する場合にグループの間を区切る
- ランクD:破線、細め、うすめ。行の間を区切る。もっとも弱い区切り線
また、本書では罫線は行を区切るときにのみ使用し、列には使用しないことを基本としているが、ときに列にも必要なケースがあり、そういう場合には使用している
図版タイプ:複合的な表。
さまざまなタイプの図版をそのセルの内部に格納して、複合的な表を形成する。本書では、
- 帯グラフ、
- 円グラフ、
- 地図
にとどまらず、
- 敷地図や
- 建築図面、
果ては、
- 体系図など、
あらゆるタイプの図を内部に収めている。そのために伸び縮みする姿を見ると、「表」というフォーマットの柔軟性の高さに目をみはるのである
図版タイプ:散布図(あるいは分布図)。
散布図は、1つのサンプルにつき2つのデータ項目の値を座標値とする点を、座標平面上に、複数のサンプル分にわたって記した図。2つのデータ項目の分布状態と、その相関関係を把握できるという特長をもつ。
本書の散布図では、似た性格をもつサンプルの集まったグループをうすい半透明の色面で表すことで、2つ以上が重なる場合でも、個々のグループの範囲を一見で把握できるようにしている
図版タイプ:体系図。
図のなかの要素と要素を線や矢印で結ぶことによって、ある計画やシステムや状況が、どのような要素とその関係から成り立っているのかを説明する図。本書ではその子タイプといえる、以下のような図を掲載している。
- 枠組図:復興事業における住宅の生産体制を、そのタイプ別に図解
- 流れ図:被災してからつぎの住宅を確保するまでの流れを、住宅損壊の程度や制度利用の選択に応じて説明
- 組織図:復興事業担当部署の組織構成が、時間の経過の中でどのように統合・分岐して変化したかを、各年次ごとの部署名と職員数を示すことで説明している
- 相関図:災害公営住宅の居住者の人間関係の変化を図解
どの図においても、流れを示す矢印など図のなかで共通化できる構成要素は、体裁を1種類に定めて統一している
図版タイプ:ファンドフロー図。
さきの〈図版タイプ:体系図〉の一種といえる。海外の事例として紹介する地域ごとに、復興事業でどのようなタイプの資金がどのような経路を通って流れたかを説明する
図版タイプ:さまざまな図。
著者側が制作した図の中には、こちらがはじめて見るタイプの図がいくつもあったので、あらためて学ぶことが多かった。個々のものが時間の経過のなかで変化していくという動的な状況を、「図」は、静止した2次元に記録して伝えることができる。その力をあらためて思い知る良い機会になった。
以下のものはそのなかの一例。
- 復興初期における計画策定や事業化のプロセスが、被災者への意向調査とともにどう進んでいったのかを、被災自治体ごとに時系列に沿って記録した表
- 共助型の災害公営住宅に入居した被災者が、ある1日をどう過ごしたのか、その生活行動を2つの時期に分けて記録し、その前後の変化をみる表
(次へつづく)
(前からのつづき)
- 災害公営住宅への入居を希望して登録した被災者が、市内のどこの地区を希望したのか、その意向の時間的変化を、震災前後における各地区の人口の変化とともにみる図
- 復興計画の事業化プロセスにおいて、ある議題が、並行する複数の主要会議の間でどう引き継がれ、住民への説明や実際の事業化へどうつながったのかを視覚化した図
複雑に込み入った図は、さきの〈図版タイプ:地図(土地利用図)〉と同じように、濃い色と薄い色の2枚のレイヤーに分けてお互いの要素が干渉しないように切り離すことによって、図のなかの要素を見えやすくしている